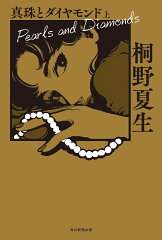Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xs642990/dark-pla.net/public_html/wp-content/plugins/bravo-neo/bravo-neo.php(12) : eval()'d code on line 647
桐野夏生『真珠とダイヤモンド』読了。
主人公は二人。
終盤にタイトルの意味が回収される形です。
バブルについての本ですが、片方の女性が浮浪者となって井の頭公園で佇むところが冒頭で、しかもコロナの影響で仕事も住処も無くした、という書き出しだったので、ずいぶんと長い期間の物語を書き切ったものだなと思って読み始めました。
ところがそれは誤解で、実質的にはバブル崩壊の中でもう片方の女性とその夫が命を落とすところで話の殆どは終わりでした。
バブルを主軸に据えた物語なのでバブルとその崩壊に伴う悲喜劇が主になるのは当然ですが、バブル以降の金融業界を過ごした、というか業界人としてあのバブルを知らない自分からすると、なにか肩透かしを食らったというか、否定されたような感もでますけどね。
無論、無いものねだりというか、逆ギレなんですけれども。
自分が会社づとめをしていたころには、まだバブルを知る人間も在職中で、役員の中には尾上縫のところに日参していたなんていう輩もいたので、少しは地続きのところもあるかな、と考えていたのですが、本書の描写が「日常」だとすると、これはまったく違うカルチャーですね。
無論、セルサイドとバイサイドの違いというのもあろうし、地場証券ならではの行儀の悪さというのもあろうし、男女雇用機会均等法が施行される前のオフィスの光景だからというのもあるでしょうけれども。
アマゾンレビューを読むと、当時の金融業界にいたという方が「感情移入し」て読んだとあり、相当にリアルさはあるのでしょう。
「あの頃が懐かしい」みたいなレビューもあったりします。
総じてそこで日本の歴史が終わっているかのようですね。
そしてそれらは夢でした、と。
あと、今となって過去を書くフィクションなので当然なのですが、登場人物のほとんどが宴の最中にすでにその終わりを感じとっているほどには不自然に賢いです。
それらもまた、それでもなお逃げられなかった、みたいなやるせなさの演出になっていますが。
しかし、九州ヤクザである山鼻の「さあ、バブルの波に乗ってどこまでいけるか。」のように、当に「バブル」という語を使ってそれを語っているのはフィクションが過ぎるような気も。
そのバブルでうまく立ち回ったはずの水矢子もまた、母親の借金の保証人になっていたことからバブル崩壊後程なくして転落を始めます。
ただ、進学校の出でありながら高卒で働くことになったのは、単に家庭環境のせいでしかなかったほどには利発な彼女なので、勝手に保証人にさせられていたことを知れば、無効を争うくらいのことはできそうなキャラではあるのですが、唯々諾々と転落していくのは少し解せません。
まあ、バブル以降のことは端折りたかったのでしょうけれども。
とはいえ福岡の女性の言葉はいつ聞いても魅力的です。
佳那の「そんなことなかとよ。」というのは、無理にマスターした福岡弁の「そげんこつなかとよ。」が、ビジネス的に上品になった、という感じなのでしょうか。
微妙な言い回しまではわかりませんが、無性に福岡に行きたくなります。
というか、中洲の女の子と話をしたくなりますね。
あ、でも篠田麻里子は勘弁ね。