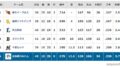Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xs642990/dark-pla.net/public_html/wp-content/plugins/bravo-neo/bravo-neo.php(12) : eval()'d code on line 647
加賀翔『おおあんごう』読了。
著者の初小説とのこと。
少年時代の父親との関係がテーマで、エピソードの一つ一つは、多分に著者の実体験に基づいているのだと思います。
それらを再構成して、中和して、解毒して、ちょうどよいフィクションにしました、という感じですね。
構成の仕方によっては、貧困DV家庭でサバイバルした少年の振り返り、みたいなことにも出来そうですが、そういうダークな道には落とさず、岡山弁のほんわかした口調と、田舎の風景でうまくごまかしてどこか昭和チックなお話に。
でも彼は1993年生まれなので、自身がモデルなら平成の出来事なんですけどね・・・。
加賀くんを初めてテレビで見たとき、とても芸人とは思えない面構えで、果たしてお笑いなんてできるのだろうか、と思ったのを覚えています。
相方の賀屋くんの人を食ったような顔とあまりに対照的で、まあ、そのコントラストがこのコンビの魅力の一つなのかな、とは思いました。
こういった幼少期の経験が、お笑いの芸風に役立っているのかどうかはわかりませんが、少なくともこうして小説としては世に出ました。
ただ本作、小学生のときの出来事が終わってから、大人になってからの記述に飛ぶのですが、その間、主人公になにか変化があったような感じがないのですね。
そこに少し違和感を持ったのですが、アマゾンレビューで「現在の著者自身と往時のご自身との距離が近すぎる」みたいな触れ方をしている方がいて、合点がいきました。
悪く言うと、小学生当時の記述と現在の記述が同じ視点。
これは、その間に成長が無い、という言い方も出来るし、あるいは今の大人の視点で昔を書いてしまっている、という言い方もできます。
ただ、こういう限界家庭に育った子どもというのは、どこか最初から出来上がっていてしまっているようなところもあったりして、本当に子どもであった当時から、変わらずこの視点だったのかもしれず、そこはなんとも言えないんですよね。
それにしても、最後まで救いのないお父さんです。
さくらももこさんは、ちびまる子ちゃんで友蔵じいさんを愛くるしいキャラとして描きましたが、実際の友蔵さんはかなりの堅物というか、家族の中での嫌われ者だったようで、彼女の随筆には死んだときにお姉ちゃんと大喜びしたエピソードが書かれています。
大人になってから身近な人を描くのであれば、そういうやり方もあったとは思うのですが、本作はそういうタッチとも無縁。
父から携帯の着信拒否やLINEブロックをされ、今後も一切関わりは持たないだろう、というエンディング。
これが実際のエピソードに基づくものだとしても、いや、そうだったとしたらなおのこと、もう少し書きようはあったのかな、なんて思ったりはします。
無論、こういう書き方は良くない、というわけではないです。
親族突き放し系の極北として、なかにし礼さんの『兄弟』がありますし。
まあ、あれは本人が死んだから書けたわけですね。
なにせ「兄さん、死んでくれてありがとう」ですからね。
そういう意味では、過去を再構成するには少し早かったのかもな、という感が無きにしも、な一冊。