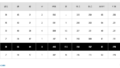Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xs642990/dark-pla.net/public_html/wp-content/plugins/bravo-neo/bravo-neo.php(12) : eval()'d code on line 647
白石一文『投身』読了。
2023年5月出版の描き下ろし作品です。
2022年の夏から翌年の正月までが設定の物語。
コロナ禍とその前後を振り返っているところからして、文学の世界にもようやくコロナ後がやってきたのだな、と感じます。
ただ、定食屋を経営している主人公であってすらも、コロナ禍でのエピソードの振り返りはあまりなく、しばらく休業を余儀なくされ経営が厳しかった、というだけ。
それ以上でもそれ以下でもなく、コロナ禍とは多くの人にとっては特段のエピソードもなく単に3つ歳を取っただけ、といった印象となります。
そうではなかったのは、PCR検査で儲かった「〇し◯んクリニック」とかそういう界隈くらいでしょうかね。
基本的には主人公である「旭」を中心に話は進むのですが、当初はこの「旭」が男なのか女なのかもわからず、なかなか入り込めなかったのでした…。
無論、読み進めるうちに主人公の家族構成とか、後々のキーパーソンになる主人公が借りている店舗・自宅の大家でもある「二階堂」との関係などはわかるようにはなるのですが、それがわかってから、再度最初からざっと読み返してみたりとか、そういうことはありました。
でも、無駄な登場人物は出てこないのですね。
最後に唐突に登場する原という女の子に至るまで、その唐突さも含めて無駄ではないわけで。
歳下の彼との思い出も、旭がその定食屋のメニューを固定している理由として回収される程度には重いし、父母のエピソードもその祖父母の代の話から始まったときには大風呂敷すぎるかと感じたものの、終盤には相続事案に絡めてうまく二階堂氏との接点に繋がってくるし、隙がないのですね。
まあ、妹の夫との関係が始まってしまうことになった、媚薬代わりになるほどの蜂蜜については、そんなものが本当にあるのかどうかは存じ上げませんが…。
昔彼女が池上通り沿いのマンションに住んでいたこともあり、品川とは言っても、あの界隈のごちゃごちゃしい感じとか、そのあたりで幅を利かせているという不動産屋然とした二階堂氏の佇まいとかはなんとなくわかります。
わかるだけに、結局はあんな最後になった背景についても、ありうるよなぁ、なんて納得してしまうのです。
旭の側からはわからないでしょうけれども。
というわけで、作品としても最終章だけ二階堂氏の告白になります。
で、そこですべて興ざめになるというか、ああ、こんな俗物の物語だったのか、と読者としてはがっかりさせられます。
旭目線では、いなくなった側の心の内側まではわからないわけでうまい演出です。
その前章では彼女は彼女で、残された者の常として色々と考察はしているわけですが。
でも、当人である二階堂目線だと、別に深みも無い。
単に金にあかせて死を前に我欲を押し通しただけ。
別に信仰も教養もない富裕層が、ただ一人で死を意識したときに頭をもたげる発想なんて、でもそんなものかもしれないな、とも思うのですね。
多分二階堂氏自身は、特にSMにも興味があったわけでもないのでしょう。
死を悟り、そこそこの金があって。
そうしたら死ぬ前にこういうこと、自分も考えちゃうかなぁ、なんて、呆れながらも納得したのでした。
金を持った俗物の最後として、人生を考えてしまう一冊。