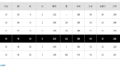Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xs642990/dark-pla.net/public_html/wp-content/plugins/bravo-neo/bravo-neo.php(12) : eval()'d code on line 647
田原 総一朗、ケント・ギルバート『激論 アメリカは日本をどこまで本気で守るのか?』読了。
副題が「目前に迫る中国の脅威!」ということで、こういう本は多分10年後くらいに読むと面白いのかなと思います。
後から振り返ってみて、2020年代前半の空気感ってこんな感じだったよね、という。
日本語はネイティブレベルのモルモン教徒の親日アメリカ人と、政治家とのコネでギョーカイを生き抜いてきた司会業のお爺さんの対談です。
二人とも別に国際政治の専門家というわけでもなく、チャイナ畑というわけでもありません。
意見が真っ向から対立することもなく、現実的に考えたらこうだよね、という見方をお互い確認しあっている感じが心地よいです。
その心地よさは、どこまでいってもアメリカ人なので日本のことは傍目になるケントさんと、おそらく10年後にはこの世にはいないか、そうでなくとも第一線にはいないであろう田原さんが出す空気感で、偽悪的に言えば当事者意識が欠けているからですね。
でも、二人とも日本の将来についてさほど悲観していないのも良いです。
ようやく目覚めたか、という呆れ感みたいなものは感じられますが。
無論、目覚めたのは日本だけでなくアメリカも。
日米が手を携えてチャイナという怪物を育ててきてしまったわけで、その責任は重いのです。
ただ、少し田原さんの認識が違うかな、と感じるのはチャイナが覇権への意識を持ち始めたのは江沢民になってからでも習近平になってからでもなく、建国当初から。
CIA職員として中共と対峙してきたマイケル・ピルズベリーの『China 2049』を読むとわかりますが、初めからチャイナが見ていたのはアメリカだけで、日本のことは端から意識していませんね。
それは、日本が世界第2位の経済大国であったときでもそうで、当時でもチャイナは日本を都合よく搾取する対象としてしか見ていません。
日本の地位を奪おうとかそういう意識ではなく、結果として今日本を抜いた状況にあるというだけ。
もし本当に彼らの覇権志向がせいぜいこの20年くらいのものだと今もって理解しているのなら、田原さんは相当に工作の容易な対象だったのでしょうね。
ケントさんからは「いつ、親中派から転向したんですか?」などと言われていますが。
そういう意味でも、今の米中対立を米ソ冷戦時代のメタファで見るのは、安直というか危険かもしれません。
一応田原さんからは、あのときと比べるとアメリカの相対的な国力は落ちているから同様に見てはいけない、というエクスキューズは入っていますが、80年代は経済面では日本から追い上げを食らっていたはず。
軍事的にはソ連と、経済的には日本と対峙していたのが80年代のアメリカで、国力が増し世界の中で一強となったのはソ連が崩壊し、冷戦が終結した後の話じゃないでしょうか。
で、もっと言うと冷戦期においては日本は別に覇権国家になろうとはしてないですからね。
どこの世界に基地をおいて守ってもらっている国に対して覇権を挑もうとする国があるのでしょうか、という話ですよ。
でも、そんな国の半導体産業を完膚なきまでに潰したのがアメリカという国なのでした。
それもまた彼の国の工作の結果なのだ、なんていうのは陰謀論が過ぎるでしょうかね。